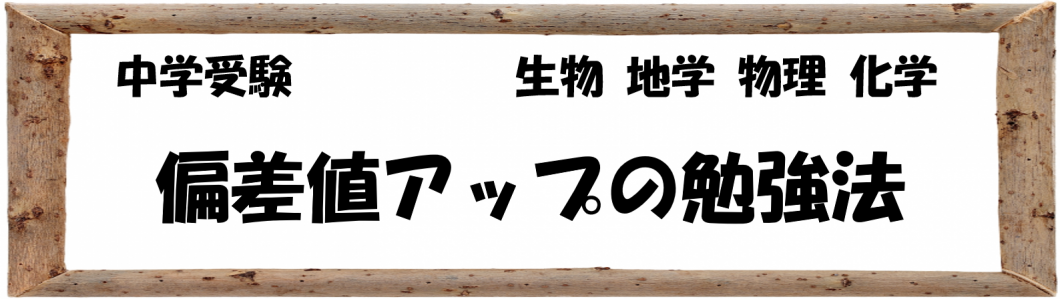中学受験の理科 栄養と肥料のちがい
ユーチューブによるワンポイント・レッスンを行っております。重要ポイントを1テーマ2分で解説するものです。次々と公開していきますので、チャンネル登録をお願いします。
⇒ ユーチューブによるワンポイント・レッスン
△上のリンクをクリック△

2022/12/08
-300x169.gif)
【植物は光合成で栄養を作ることができるのに、なぜ種子に栄養が必要なの?】
最初に思い出すのは、メダカです。生まれたばかりのメダカの赤ちゃんは、おなかに卵の栄養がついていました。
えさを食べなくても2~3日は生きていけるように、お母さんが卵に栄養を多めに残しておいてくれたのでした。
メダカは、生まれた瞬間から敵に囲まれています。親に見つかっても、食べられてしまいます。
生まれてすぐに「泳ぐ練習」と「えさを取る練習」をしなければ、生き残ることはできません。一人前になるまでの栄養が、必要なのでした。
植物も同じです。生まれたばかりの幼芽は小さくて、生きていくための光合成もわずかしかできません。
一人前になって充分な酸素と栄養を作るまでの間は、生きるための栄養が必要です。それを、お母さんが種子の中に残しておきました。
私たちは、毎日ごはんを食べています。ごはんは、イネの「はい乳」です。イネのお母さんが、子供のために残しておいた栄養です。
それを私たちが食べているのです。食べる時には、「いただきます」と言いましょう。
本番までに与えられた時間の量は同じなのに、なぜ生徒によって結果が違うのか。それは、時間の使いかたが異なるからです。どうせなら近道で確実に効率よく合格に向かって進んでいきましょう! くわしくは、以下からどうぞ。
⇒ 中学受験 理科 偏差値アップの勉強法
栄養と肥料の違いは何?
3大栄養素と5大栄養素を、覚えていますか? 炭水化物・脂肪・タンパク質が3大栄養素。さらにビタミンとミネラルを加えて5大栄養素です。
炭水化物と脂肪は、生きるためのエネルギーのもとです。タンパク質は、体の材料のもとです。ビタミン・ミネラルは体の成長を助け、調子を整えるはたらきをします。
動物は栄養を自分で作ることができませんから、5大栄養素すべてをバランス良く取る必要があります。いっぽう植物は、ほとんどの栄養素を自分で作ることができます。
例えば、植物がタンパク質を作るとします。タンパク質を作るためには「チッソ(N)」という部品が必要なのですが、それを植物は自分で作ることができません。ですから、「チッソ(N)」を外から吸収するしかありません。
そのような成分を含んでいるのが肥料です。植物にとって肥料の3大成分は、チッソ・リン酸・カリウムといわれています。
では、自然の世界で肥料を作るのは誰なの?
それが微生物です。微生物は「土の中」にも「水の中」にも「空気中」にも、どこにでもいます。
この微生物が動物の「死がい・ふん・にょう」を分解して、結果的に植物が必要とする肥料ができます。
こうして、陸上・水中ともに「食物連鎖」ができあがります。
植物→草食動物→肉食動物→微生物→植物 この中の誰かがいなくなれば、すべてがほろんでしまいます。
みんなに役割があるというのが、おもしろい所です。
2020年10月の赤本・2021年11月の青本に続き、2022年12月エール出版社から、全国の書店で偏差値アップの決定版ついに公開!
くわしくは、以下の記事をご覧ください。
⇒ 中学受験 理科 偏差値アップの勉強法
スポンサーリンク
スポンサーリンク