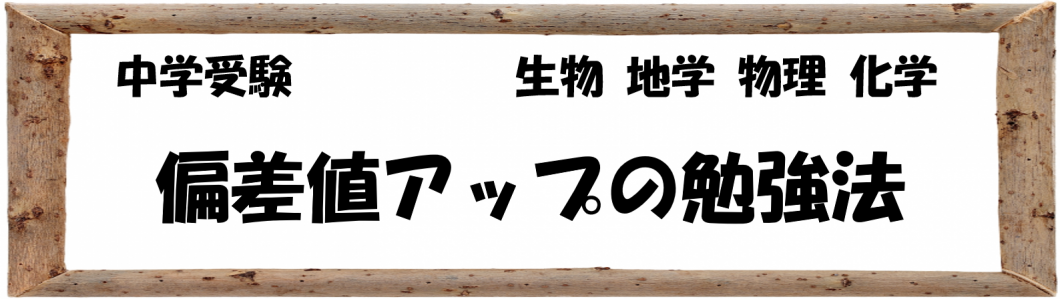中学受験の理科 気体の発生
ユーチューブによるワンポイント・レッスンを行っております。重要ポイントを1テーマ2分で解説するものです。次々と公開していきますので、チャンネル登録をお願いします。
⇒ ユーチューブによるワンポイント・レッスン
△上のリンクをクリック△

2022/12/08
酸素が大事なことはだれでも知っています。では気体の性質として、酸素とともに必ず二酸化炭素も学習するのはなぜなのでしょうか。
二酸化炭素は、空気中にわずか0.038%しか含まれていません。しかも地球温暖化の原因が二酸化炭素といわれるくらいですから、むしろ大事ではないと思ってしまいそうです。
酸素がなければ、地球上の生き物はいなくなってしまいます。同じように二酸化炭素がなくても、地球上に生き物はいられません。
理由に、気がつきましたか? 気がつかなかった人は、「植物編(呼吸と光合成)」へどうぞ。以下のリンクをクリックしてください。
⇒ 中学受験の理科 植物の呼吸と光合成~これだけの理解で基本は完ペキ
本番までに与えられた時間の量は同じなのに、なぜ生徒によって結果が違うのか。それは、時間の使いかたが異なるからです。どうせなら近道で確実に効率よく合格に向かって進んでいきましょう! くわしくは、以下からどうぞ。
⇒ 中学受験 理科 偏差値アップの勉強法
三角フラスコの中にあるガラス管は、なぜ一方が長くて一方は短いのでしょう?
.png)
これは暗記するのではなく、理解してしまえば当たり前であることが分かります。
「過酸化水素」が分解 → 酸素 + 水
「塩化水素」と「炭酸カルシウム」が結合 → 二酸化炭素 + 塩化カルシウム + 水
どちらも水ができます。
つまり、実験が進むにつれて、三角フラスコの中には水がたまっていくのです。
酸素も二酸化炭素も、「ろうとの中にある液体」と「三角フラスコの中で待ちかまえている固体」がふれ合って発生します。2つが、ふれなければなりません。
ガラス管を長くしておけば、実験で水がたまっても2つはふれます。もう一つのガラス管は短くないとやがて水につかってしまうので、発生した気体の行き先がなくなってしまいます。
気体が発生して、最初に出てくる気体を集めない理由。
酸素(重さは空気の1.1倍)も二酸化炭素(重さは空気の1.5倍)も、空気より重いです。ですから、三角フラスコの底から上に向けてたまっていきます。
もともと三角フラスコの中にあった空気は、酸素や二酸化炭素におし上げられてガラス管から出ていきます。
つまり、はじめにガラス管から出てくる気体は空気です。実験では、最初に出てくる気体(空気)は集めません。
次のテーマは、気体の発生に関する計算問題の解き方です。以下の記事を、ご覧ください。
⇒ 中学受験の理科~気体の発生や金属の燃焼で確認する化学計算問題の基本
2020年10月の赤本・2021年11月の青本に続き、2022年12月エール出版社から、全国の書店で偏差値アップの決定版ついに公開!
くわしくは、以下の記事をご覧ください。
⇒ 中学受験 理科 偏差値アップの勉強法
スポンサーリンク
スポンサーリンク