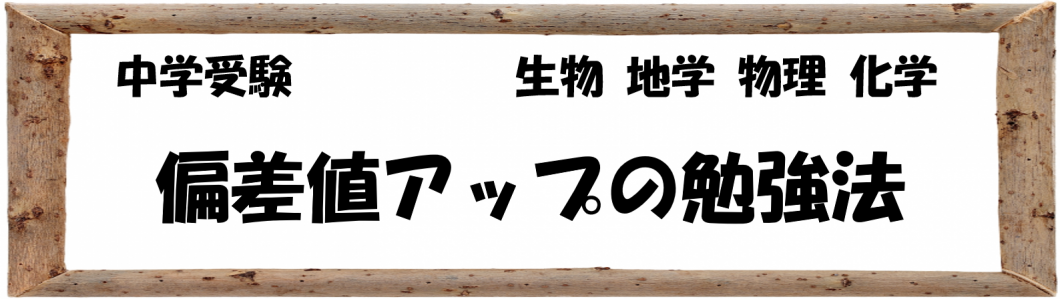中学受験の理科 浮力~頭を整理するため最初にするべき事とは!
ユーチューブによるワンポイント・レッスンを行っております。重要ポイントを1テーマ2分で解説するものです。次々と公開していきますので、チャンネル登録をお願いします。
⇒ ユーチューブによるワンポイント・レッスン
△上のリンクをクリック△

2023/07/23
要するに、浮力って何? と聞かれた時に、
「浮力とは、物体がおしのけた液体の重さ」
「おしのけたとは、物体がつかっている部分」
と10秒以内で言えるようになってください。
これを答えるのにまごついていているようでは、本番の試験で点を取れるはずがありません。
いま物体がつかっている部分には、もともと液体があったはずです。
それを物体がおしのけました。もともとあったのに、物体におしのけられた液体。その液体の重さが浮力です。
「物体の体積」「物体の重さ」「液体の体積」「液体の重さ」「おしのけた」「おしのけられた」 これらのうち何が浮力に関係するのか、頭の中を明確にして問題に向かいましょう。
頭の中を整理するよりも、素早く言えるようになるほうが先であることを、お忘れなく!
本番までに与えられた時間の量は同じなのに、なぜ生徒によって結果が違うのか。それは、時間の使いかたが異なるからです。どうせなら近道で確実に効率よく合格に向かって進んでいきましょう! くわしくは、以下からどうぞ。
⇒ 中学受験 理科 偏差値アップの勉強法
浮力の問題
.png)
この物体を支えているのは水だけなので、浮力は50gという事が分かります。
「浮力とは、物体がおしのけた液体の重さ」ですから、物体は50gの水をおしのけました。
50gの水をおしのけたという事は、50㎤の水をおしのけたわけです。
「おしのけたとは、物体がつかっている部分」ですから、つかっている部分は50㎤。
つかっている部分の体積は物体の半分の部分なので、物体の体積は100㎤となります。
仕上げとして、問題演習に取りくんでみましょう。
【問題演習:浮力1】
⇒ 中学受験の理科 浮力・重さ・体積を確認する問題演習と解説【1】
【問題演習:浮力2】
⇒ 中学受験の理科 浮力・重さ・体積を確認する問題演習と解説【2】
【問題演習:浮力3】
⇒ 中学受験の理科 浮力・重さ・体積を確認する問題演習と解説【3】
「ばね」のテーマについては、以下の記事で確認してください。
⇒ 中学受験の理科 ばね~これだけ習得しておけば基本は完ペキ!
2020年10月の赤本・2021年11月の青本に続き、2022年12月エール出版社から、全国の書店で偏差値アップの決定版ついに公開!
くわしくは、以下の記事をご覧ください。
⇒ 中学受験 理科 偏差値アップの勉強法
スポンサーリンク
スポンサーリンク